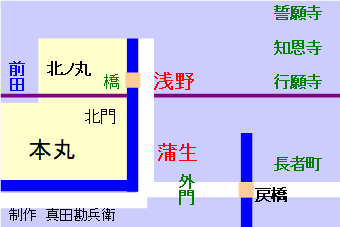
| 本当に実在したの?絵画史料に描かれているような聚楽第天守 |
|
重要なお知らせ
現在利用しているホームページのサービス終了に伴い、当HPは9月上旬に移転する予定です。 現在御覧になっているページは10月1日以降は見られなくなります。 詳細はメインページに記載しているお知らせを御覧ください。
|
聚楽第に関する史料は限られています。聚楽第の天守に関してはさらに史料が少ないです。
そのため、「聚楽第図屏風」など絵画史料を根拠に聚楽第本丸北西隅には5層(もしく4層。層は重とも表記)の天守閣があることは周知の事実のように信じられ、書籍などで聚楽第について扱う場合はこれら絵画史料を根拠に「聚楽第には5層の天守閣がある」と記載されることが多いです。
しかし、このHPを制作する過程で聚楽第の天守閣に関する伝承は少なく、聚楽第跡地に聚楽第の堀や庭園、門に関する地名が存在するに関わらず天守閣を由来とする地名は存在せず、聚楽第行幸に関する政権が制作した公式記録、外交使節や大名など聚楽第に来た人が残した記録に「天守閣に登った」という記述がないことに気づき、聚楽第に「聚楽第図屏風」など描かれているような5層の天守閣が本当にあったのか疑問を感じました。このページでは聚楽第に絵画史料のようなの天守閣の存在したのか考えてみたいです。
天守閣という言葉は後世に作られたものです。厳密には天守です。天守は天主や殿主と表記されることもあります。
同一ページ内で天守閣を示す言葉が複数あるとややこしくなりますので、文献史料などからの引用や固有名詞を除き、以下は天守と表記します。
なお、2023年11月現在、グーグルマップでは一条通裏門通東入ル南側の民家の建物内に「聚楽第天守跡」と記載されています。民家の敷地内のため入れません。記載されている建物や付近の道路沿いには天守跡を示す石碑や駒札はないです。また、記載されている付近に天守台があった地形的な痕跡はないです。行かれても何もないです。
天守もしくは本丸北西隅櫓の推定位置は裏門通一条下ルの西側です。グーグルマップの「聚楽第天守跡」の位置は明らかに誤りです。そもそも、民家の建物内という自由に入れない場所に聚楽第天守跡」という史跡があると記載した意図はわからないです。
◆現時点での聚楽第の天守に関する情報の概要
まず、私が把握している範囲で聚楽第の天守に関する情報を整理します。
○絵画史料などに描かれている聚楽第の天守
聚楽第を実際に見て描いたという伝承があるのが三井記念美術館蔵「聚楽第図屏風」です。聚楽第本丸の左側奥、上を北と考えると本丸北西隅に天守が描かれています。
「聚楽第図屏風」は聚楽第にとって重要イベントである聚楽第行幸が描かれていないという点から、成立年代は1度目の聚楽第行幸が行われた天正16年(1588)4月以前と推測されています。聚楽第行幸以前でも天正15年(1587)9月に秀吉が大坂城から聚楽第へ大行列を引き連れて移住したように、1度目の聚楽第行幸以前でも図屏風の題材となりうる出来事はあります。
また、行幸以後に行幸行列を描くか描かないかは注文主が決めることであり、「行幸以後に描かれているなら必ず行幸を描くはず」という見方は客観的なものではないです。
行幸行列を描くと屏風に描く人数は大幅に増えます。屏風という性質上、行列を忠実に描く必要はないですが、行列の雰囲気を出すためには行列の構成と供奉者の乗り物と衣装など最低限度のことは把握していないとならないです。絵師が行列を見て記録していなければ、調べる手間もかかります。
行幸行列を描かない構図にする場合より費用は高くなります。制作期間は行列を描くことで長くなります、行幸以後に注文主が金銭的、もしくは制作期間を長くできないなどの理由で行列を描くように頼まなかったという可能性はあります。
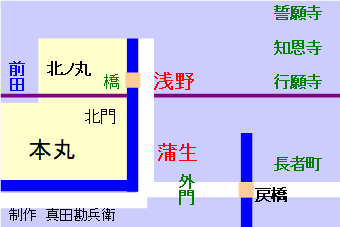
屏風絵という性質上、南北のラインが屏風の上に対し右へ少し傾いています。上図は南北のラインを真上に直し、聚楽第周辺部分に限定して、描かれているもののをわかりやすく配置し直しました。
赤字の人物名は町名由来として残っている人物、青字の人物はそれ以外、緑字は大名以外で町名由来として残っているものを表しています。(聚楽第関連の町名に関してはこちらのページをご覧ください)
前田屋敷、北ノ丸南堀(本丸北堀を兼ねています)、浅野を由来とする弾正町、知恩寺は現在の一条通に面しているため、この図屏風では描かれていない一条通のラインを意識していると考えられるため、紫色線で一条通のラインを加筆しましました。
この図屏風は聚楽第の東堀から土橋を渡り、第内に入った場所に門が描かれています。『駒井日記』から本丸には北門、西門、南門があることがわかります。北門は北ノ丸、西門は西ノ丸、南門は南二ノ丸へ通じる門と推測できます。この図屏風で描かれている聚楽第は東堀から土橋を渡った先に曲輪があり、北門を通り本丸へ入る構図です。この曲輪には御殿と隅櫓が描かれています。そのことから、東堀から土橋へ渡って入った曲輪は北ノ丸ということがわかります。
中井均氏は「城郭史からみた聚楽第と伏見城」(『豊臣秀吉と京都』 編 日本史研究会 文理閣)の中で、『鹿苑日録』の文禄2年(1593)8月1日にある「北方新御殿」が北ノ丸に該当し、北ノ丸は文禄2年に新造された曲輪とされています。
ただ、『鹿苑日録第3巻』(編 辻善之助 太洋社)では「北方新御殿」という記述は文禄2年ではなく翌年の文禄3年(1594)8月1日ですから、文禄2年とされたのは中井氏の誤記です。この記述を北ノ丸造営の根拠と考える中井氏の説に従うと、北ノ丸が造営されたのは文禄3年頃です。
秀吉は内野と呼ばれていた平安京大内裏跡地を意識し、内野の北東部分に収まる位置に聚楽第を造営しました。しかし、北ノ丸のみ内野の北限である一条通より北にあります。そのことも増築であるという中井氏の説を裏付けます。北ノ丸の造営時期を「北方新御殿」という記述を根拠にする中井氏の説に従えば、北ノ丸が描かれている「聚楽第図屏風」の成立時期は文禄3年以降になります。
図屏風の1扇の中央、長者町と附箋がある町家の北(上を北と考えた場合)に3つの寺が描かれています。附箋から上から順に誓願寺、革堂(行願寺)、百万遍(知恩寺)ということがわかります。これらの寺は小川(こかわ)沿いにありましたが、天正18年(1590)の寺町形成、もしくは翌年の堀川から東が大名屋敷街に変わった時(この区間の大名屋敷の配置はこちらのページを参照)に立ち退きました。これらの寺があった小川通の元誓願寺通から一条通周辺には誓願寺があった由来の元誓願寺通や革堂があったことが由来の革堂町などこれらの寺に由来とする地名が現在も残っています。
北ノ丸が造営された文禄3年時点では小川沿いの3つの寺は移転済みです。聚楽第に北ノ丸があることから聚楽第の姿は文禄3年以降、聚楽第の東側の風景は天正19年(1591)以前と図屏風の中で描いている風景の年代が異なるという矛盾があります。文禄3年に造営されたと考えられている北ノ丸が描かれていることから、「聚楽第図屏風」の成立年代は通説の天正16年以前ということを根本的に見直す必要があります。
また、2008年に新潟県上越市の所有者が鑑定に出したことで2009年に歴史的価値が判明した「御所参内・聚楽第行幸図屏風」(私は略称を上越本と命名。以下 上越本と記載)などの絵画史料にも本丸の北西角(図屏風の上を北と考えた場合)に天守があります。
上越本の調査をされた狩野博幸教授は2009年秋の上越市立総合博物館での特別展のリーフレットの中で、成立推定年数は秀吉死後(1598)以後の慶長年間(1615)とされています。
上越本の天守は他の絵画史料で描かれている聚楽第の天守と異なり、塔に近い形状をしています。天守は分類上、望楼型と層塔型があります。「聚楽第図屏風」などの天守は望楼型ですが、上越本のみ天守は層塔型の天守を想定して描いていると推測できます。
層塔型の天守閣は『図説 天守の全て』(監修 三浦正幸 学研)によると慶長9年(1604)から慶長13年(1608)に築城された今治城の天守が最初で、この天守は慶長15年(1610)に丹波亀山城に移築されました。層塔型はそれ以後に築城された城の天守でよく用いられる型です。聚楽第があった当時は層塔型の天守は存在しません。まして層塔型の天守でも上越本の天守のように塔そのもの形ではありません。
上越本の聚楽第の推定構造は発掘調査と史料に基づき作成された聚楽第復元図など、既存の研究や他の絵画史料とかけ離れている独創的です。私の考えとしては絵師が聚楽第を見て描いたとは考えられません。上越本はこちらのページで解説しています。
つまり、現存している聚楽第を描いた絵画史料は聚楽第があった頃に描かれた、もしくは絵師が聚楽第を見て描いたと証明されているものはあります。そのため、絵画史料だけを根拠に聚楽第には5層の天守が存在するという断定はできません。
○文献史料上の聚楽第天守
吉田神社の神主の吉田兼見の日記『兼見卿記』の天正18年(1590)1月18日の項で豊臣秀吉の側室の摩阿姫(前田利家の三女。後に加賀殿と呼ばれる)を吉田兼見は「聚楽天主」と記載しています。このことから聚楽第に天守が存在し、吉田は彼女が聚楽第天守に住んでいたという意味で「聚楽天主」と記載したという考え方もできます。ただ、吉田が摩阿姫を「聚楽天主」と記載した意図は不明です。
山科言経の日記『言経卿記』では文禄元年(1592)11月29日には、「牛刻ニ殿主へ渡御、則参了、(中略)、悉殿主之内、金已下被見了、御酒有之」という記述から、山科らは天守へ行き、金など見物しました。「御酒有之」とあることから山科らはその後、前年に関白職と共に聚楽第の主の座を引き継いだ豊臣秀次から昼食を振舞われたのでしょう。振舞われた場所が天守であるかはこの記述だけでは判断できません。
秀次が彼らを天守へ招いた目的は「金已下被見了」とあることから黄金(天正大判か金塊、砂金など形状は不明)を見せるためです。天守へ招かれたのはこの日の午前中に行われた源氏物語の講釈の講師役の連歌師の里村昌叱と、里村の養父、講釈を聴いた山科らです。山科や連歌師の里村昌叱らなど名前が掲載されている7名とその他4、5名が天守へ行きました。
山科は記載していませんが、秀次と秀次の近習達も天守に来ているはずです。その人数も加えると少なく見積もって15から20名ぐらいは天守にいたと推測できます。天守にはそれぐらいの人数が入れる広さがあったようです。この日は秀次の文化活動に関わる人達が聚楽第に集まり、黄金を見るために天守へ行ったことがわかります。
秀次の祐筆である駒井重勝の日記『駒井日記』では文禄4年(1595)4月5日に、「御殿主之床に黄成段子」という記述があります。天守に床の間の存在が確認できます。床の間と座敷はセットのため座敷があることがわかります。床の間に飾られている段子(どんず。緞子とも表記される)は絹織物の一種で、中国からの輸入品が主です。日本国内では天正年間(1573から1591)から堺で生産が始まりました。秀次は貴重な品である段子を飾ることで権威を示したようです。
天守を殿主と記載することもあります。上記三つの史料から「聚楽天主」という建造物が聚楽第に存在し、内部に床の間と座敷があることがわかります。摩阿姫の居住スペース、山科らが黄金を見た場所、段子が飾ってある床の間がある座敷が同一の部屋か異なるのか、同一であるならば同じ階にあるのかなどは、これだけは判断できません。
ちなみに駒井は『駒井日記』の文禄4年(1595)4月10日に聚楽第の各曲輪の名称と聚楽第の大まかな広さを記載してますが、天守に関する記述はありません。
天正16年の聚楽第行幸の公式記録の『聚楽行幸記』(『聚楽第行幸記』とも)には「瑤閣星を摘てたかく」という抽象的な表現がある記述があります。聚楽第に天守があるという前提でこの箇所を読めば瑤閣を天守と解釈し、この記述が天守がある根拠になりえます。しかし、瑤閣が具体的に何を指しているのか不明です。隅櫓や御殿など聚楽第にある他の建物を指している可能性が否定できず、この記述は聚楽第に天守があるという根拠にはできないと思います。
『聚楽行幸記』は様々な写本がありますが、大阪城天守閣蔵「聚楽行幸記」は秀吉の朱印があることから原本と考えられています。竹内洪介 石塚晴通「大阪城天守閣蔵『聚楽行幸記』解題・翻刻」(『古代中世文学論考第38集』 編 古代中世文学論考刊行会)に解題と翻刻したものが掲載されています。
○地形的な痕跡はなし
聚楽第跡地には松林寺境内の落込みや土屋町通中立売下ルの聚楽第外堀跡の落ち込みのように人為的に落ち込んでいる箇所があります。
|
松林寺境内の落ち込み
|
聚楽第外堀跡の落ち込み |
天守の土台部分である天守台は通常は5mから20mぐらいの高さがありますが、聚楽第跡地には「ある地点の周囲が他の地点に比べて明らかに高い」というような天守台が存在したことを窺わせる地形的痕跡は残っていません。
寛永元年(1624)頃成立の「京都図屏風」から聚楽第破却から約30年後でも聚楽第内堀が残っていることがわかりますが、天守台跡に該当するものは「京都図屏風」には記載されていません。もっとも、本丸に存在したはずの隅櫓も記載されていないため、「京都図屏風」の聚楽第の堀の形は正確性に疑問はあります。
○聚楽第跡の表面波探査と天守の位置
2015年に京都大学防災研究所などの共同チームが聚楽第跡地で表面波調査が行われました。その結果は京都市考古資料館で京都大学防災研究所と共同で2016年春の速報展「聚楽第跡の表面波探査」で公開されました。この速報展の配布資料によると本丸北西隅にあたる裏門通一条の南へ25m地点から75m地点でマウンド上の高まりを検出しました。
表面波調査に基づく聚楽第跡復原図は京都市文化財ブックス第31集『天下人の城』の「図26聚楽第跡復原図」などを御覧ください。
配布資料によると絵画史料を根拠に聚楽第の天守が本丸北西隅にあるという前提でこの高まりを天守台によるものとしています。
昭和49年(1974)に大宮通一条下ル東側の工事現場から花崗岩の礎石が9個見つかり、この場所に隅櫓か堀に架かる橋の橋脚があったと考えられています。当時の多くの城郭では隅櫓があり、工事現場が本丸北東隅に当たることから、この礎石は現在は隅櫓のものと考えられています。
西ノ丸と隣接している聚楽第本丸南西隅には隅櫓はないと考えます。
本丸の北東隅と南東隅に当たる場所では表面波探査が行われていないですが、隅櫓があると考えられているため本丸北西隅のように本丸から突き出しいるスペースはあるはずです。天守があるとされている本丸北西隅の本丸から突き出しているスペースが北東隅と南東隅より広いかわからないです。つまり、現時点では北西隅に天守があるとは断定できないです。
聚楽第から1キロ東には禁裏御所と公家町があります。聚楽第行幸の行幸行列は(コース詳細はこちらのページ参照)では堀川通から現在の下長者町通を西に進み、現在の下長者町黒門付近にあったと推定される東外門を通過、南二ノ丸東堀の堀沿いの道を南下します。行幸行列が最初に目にする聚楽第の建物が聚楽第南東隅櫓です。南東隅櫓が本丸の他の隅櫓よりも立派なものである可能性は考えられます。
表面波調査に基づく聚楽第跡復原図では本丸南東隅の梅雨の井で有名な路地の北側付近に北西隅の本丸から突き出したスペースより広いスペースがあります。「絵画史料では聚楽第の天守は北西に描かれている」という思い込みを捨て、表面波調査に基づく聚楽第跡復原図を見直すと行幸行列が目の前を通過するという重要な場所である南東隅のこのスペースに天守があるようという考え方もできます。
もっとも、本丸南東隅のスペースは表面波探査が行われていないため、このスペースのどれだけの部分を隅櫓が占めているか不明です
現時点では天守の正確な位置は不明です。
○その他
聚楽第天守に関する遺構伝承は桜井成広氏が唱えた西本願寺飛雲閣のみです。後述しますが、それ以外に聚楽第に天守が存在したという伝承ならびに聚楽第の天守を由来とする地名は存在しません。
ちなみに、一般的に聚楽第の天守があると考えられている聚楽第本丸北西隅跡付近の町名は北新在家町と南新在家町、今新在家町という天守とは全く無関係な町名です。
◆文献史料の聚楽第の天守=聚楽第図屏風等に描かれている5層の天守閣か?
前記文献史料から聚楽第に天主もしくは殿主と呼ばれる建造物があったことがわかります。しかし、現時点の情報だけでは、その建造物の位置や高さなど概要に関してはわかりません。
5層の天守が存在するなら3つの疑問点があります。この疑問点から、文献史料の聚楽第の天主と殿主=「聚楽第図屏風等に描かれている5層の天守閣」とできるのか、否かということを検討します。
○疑問点1 なぜ聚楽第の天守に関する伝承や地名がないのか?
聚楽第に絵画史料に描かれているような高層の建物である天守が実在するならば、城下町の町地の聚楽町を含む洛中の大部分で見えたはずです。存在していれば外部から聚楽第の天守の位置を特定することは容易で、当時の人々の記憶と記録に残り、天守に関する地名と伝承が残ったはずです。
しかし、天守に関する伝承と地名はありません。
a 聚楽第の天守に関する遺構伝承の少なさ
聚楽第の遺構と伝わるもの(伝承レベルであり、遺構と証明されたものは現時点では一切ありません)が多いにも関わらず「聚楽第天守は○○城に移築された」という伝承はないです。
桜井成広氏は西本願寺飛雲閣が聚楽第の天守を移築したという説を唱えられています。飛雲閣が聚楽第の遺構という伝承は江戸時代からありましたが、「天守」という部分は桜井氏が「聚楽第図屏風」に描かれている天守と飛雲閣の外観が似ていることを根拠に付け加えたものです。
聚楽第破却の翌年である文禄5年(1596)の伏見大地震で本願寺(現在の西本願寺)は御堂が倒壊するという大きな被害を受けました。飛雲閣が聚楽第から移築されたのであればこの地震の痕跡が残りますが、痕跡はないです。さらに本願寺は元和3年(1617)には境内の大半が大火災で焼失しています。仮に移築されていたとしてもこの時に焼失しています。それらのことから現在では飛雲閣は聚楽第の遺構ではないと考えられています。
聚楽第の他の建物が伏見城に移築されるなど各地で「○○城(もしくは□□寺)の△△(門、御殿など)は聚楽第の遺構」という伝承があるにもかかわらず、桜井氏が提唱するまで聚楽第の天守だけ遺構伝承がないのは不自然です。
聚楽第図屏風のような5層の天守が聚楽第に存在したなら、真偽に関係なく聚楽第天守に関する遺構伝承が残るはずです。
b 天守が存在したという伝承と地名がない
情報が少ない聚楽第にとって聚楽第に関連する地名や伝承は貴重な情報源です(聚楽第に関する地名はこちらのページをご覧ください)。しかし、聚楽第の天守を由来とする地名や天守が存在したという伝承が残っていません。
聚楽第の天守は絵画史料から聚楽第本丸北西角付近にあると考えられていますが、天守が存在したと考えられている場所の町名は北新在家町と南新在家町と今新在家町という聚楽第天守どころか聚楽第と無関係な由来を持っています。
天保14年(1843)に聚楽第研究をまとめた名倉言希は鳥瞰図の「豊公築所聚楽城之図」と平面図の「豊公築所聚楽城跡形勝」(どちらも明治時代の摸写のみが現存)を作成しました。明治17年(1884)に城戸竹次郎が模写したものなどが残っています。
「豊公築所聚楽城之図」の添え書きによると名倉はある人が秘蔵する「海北友松が描いた聚楽城之古図」を縮図にして写したものに制作当時の聚楽第に関連する地名や伝承を基にした研究成果を書き加えています。
海北友松の生年が天文2年(1533)、没年が慶長20年(1615)です。聚楽第があった当時から京都で絵師として活動していた海北が聚楽第を実際に見たことがある可能性が高いです。しかし、名倉が参考にした原図の「聚楽城之古図」は現存しないため、「聚楽城之古図」の筆者が本当に海北友松であるか、名倉が参考にした「聚楽城之古図」はオリジナルか模写か、どの部分が名倉の研究成果を反映したものわからないです。
「豊公築所聚楽城跡形勝」から江戸時代後半の聚楽第に関する地名や伝承の成立具合がわかります。例えば、現在は否定されていますが、聚楽第の遺構という伝承がある梅雨の井も記載されています。ただし、描かれている位置は平面図では現在の梅雨の井より一区画西にあります。「豊公築所聚楽城跡形勝」では現在の梅雨の井がある場所は堀の中です。
鳥瞰図では本丸北西角の2層の隅櫓の東隣に3層の建造物がありますが、平面図はこの2つの建物を1つの隅櫓として記載しています。平面図には天守に関する記載はないです。名倉が作成した江戸時代後期に聚楽第天守を由来とする地名ならびに聚楽第に天守が存在していたという伝承が存在しなかったことがわかります。
聚楽第の天守を由来とする地名と存在したという伝承がないという以外に名倉が参考にした「聚楽城之古図」に天守が描かれていないことも両図に天守を記載しなかった理由だと考えられます。名倉の両図以外の全ての聚楽第に関する絵画史料には天守が描かれていますが、江戸時代後半には聚楽第の天守を描いていない「聚楽城之古図」があったようです。
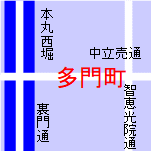
外側から聚楽第を見て、存在がわかる多門櫓(石垣の上にある平屋の長屋状の櫓)を由来と推測できる多門町が聚楽第跡地にあります。多門町の位置は森島康雄氏など発掘調査を基に諸史料を組み合わせた聚楽第城郭範囲復原案の聚楽第本丸西堀の東にあります。
多門町をはじめとする聚楽第本丸など第内に関する町名は寛永14年(1637)の「洛中絵図」で確認できます。京都全体の最古の地図である寛永元年(1624)頃成立の「京都図屏風」では聚楽第の内堀が残り、聚楽第跡地には人は住んでいません。
寛永14年(1637)の「洛中絵図」では内堀はなくなり、聚楽第城郭跡地は町地化し町名が成立しています。聚楽第の第内に関する町名は聚楽第破却から約30年後から40年後に成立しています。聚楽第本丸に庭園内の池の州浜を由来とする須浜町がありますが、池は完全に埋められずに残っていたと推測できます。
聚楽第の第内に関する町名は、森島氏など発掘調査を基に『駒井日記』など諸史料を組み合わせた聚楽第城郭範囲復原案の聚楽第の範囲内に配置されています。つまり、聚楽第に関する町名の配置は信憑性があると考えられます。
聚楽第に絵画史料にある5層の天守が存在するならば、聚楽第の建物の中では外部から位置の特定が最も容易です。天守が存在したことは人々の記録や記憶に残ったはずです。それにもかかわらず天守に関する遺構伝承が西本願寺飛雲閣のみであり、天守を由来とする地名と天守が存在したという伝承が存在しないことに強い疑問を感じます。
疑問点2 聚楽第の天守に登った記録が一切ない
前述の文献史料から聚楽第の天守(もしくは殿主)に「行った」、摩阿姫が聚楽天主と呼ばれることから「居住していた」と推測される人物がいることがわかります。しかし、天守に「登った」という記録はありません。
毛利輝元の家臣である平佐就言は天正16年7月から9月の主君の初上洛に同行し、その様子を記録した『輝元公上洛日記』を残しています。8月7日に秀吉から聚楽第での囲碁を観戦するように命じられた毛利は、
「未刻に聚楽へ出仕候碁被成御覧。其以後御座席台所迄不残見せ被参せ候駿河大納言大和大納言殿御案内者也。関白様も姫子御被成候御出て御雑談など有之」
とあり、秀吉の命令で聚楽第に出仕した毛利は囲碁を観戦した後、領地と官位の組み合わせから駿河大納言と呼ばれていた徳川家康と大和大納言と呼ばれていた豊臣秀長という政権内でも高位の2人の案内で聚楽第の座敷から台所まで残らず見学しています。しかしながら、天守に関しては一切記述はありません。
毛利は国許への帰国途中に大坂に滞在し、9月11日に大坂城を見学しました。その様子は
「此時天守を見せ被参候関白様御案内者成候(中略)金乃間銀の間銭の間御宝物の間御小袖の間御武具の間以上七重也御供の衆まで悉へ御見せ候」
とあり、毛利と御供の者は秀吉自らの案内で、金の間や宝物の間など秀吉のコレクションを展示している大坂城の天守を見学しています。
天守見学が終わった後は「其以後御座席北政所御座候間一門進被残自余ハ見せ被参候御休み所迄」と秀吉の御座の間や御休み所(寝所?)や正妻の北政所の御座の間などを見学しています。
イエズス会の宣教師のルイス・フロイスは『フロイス日本史』に天正14年(1586)年に大坂城を訪問した日本イエスズ会副管区長ら30名以上の一行の中に通訳係として同行し、一行と秀吉との謁見や秀吉の命令で城内を見学した様子を記録しています。『フロイス日本史』の引用は『完訳 フロイス日本史 豊臣秀吉篇1』(訳 松田毅一 川崎桃太 中公文庫)を使用しています。
「(高山)右近殿の先導で、我らに対して城内にある豪華をきわめた黄金塗りの他の多くの部屋や(中略)きわめて清楚で庭園とを見せるように命じた」
とあり、高山の案内で城内の様々な部屋や庭園を見学します。
「塔が内側から開かれると、関白は我らを導いていた人に、城と副塁の間を通って行くようにと命じ、我らは塔の下に赴いた。そこには鉄板で覆った小さい隠し門があり、(中略)、門が開くと、関白はその入り口に立って、伴天連および随行者全員が城内に登るよう、ただし武器を携えないようにと命じた。(中略)関白はその身分とは別に一私人のようにして司祭たちの案内役を務めた。(中略)関白はさらに自分が平素夫人と寝る場所を我らに見せた」
とあります。フロイスは天守を「主城(天守閣)および財宝を所蔵してある塔(トレル)」と表記しています。(天守閣)というのは訳者の補足です。望楼型の天守は大きな建物の上に小さな建物を乗せているように見えるため、フロイスは天守を見たことがない読み手に大坂城天守をわかりやすく伝えるため「主城および財宝を所蔵してある塔」と表現したと考えられます。
秀吉は一行を高山右近に案内で城内の広間や庭園などを見学させた後に、秀吉自らが案内役として随行員全員に天守を見学させ、天守から降りると自身の寝室まで見学させています。
フロイスは天正19年(1591)閏1月9日にインド副王使節として聚楽第の秀吉と対面した巡察史ヴァリニャーニら一行から聚楽第のことを聞き、記録しています。
『フロイス日本史』によると
「関白はその後、二人の公家に対し、司祭たちやポルトガル人に、宮殿の諸建築を参観させるように命じた。そこで一行は宮殿の主要な部分を見学したが、(中略)部屋という部屋、広間という広間、その内外と上下は言うに及ばず、台所までがその用具や机の置場に至るまで、ことごとく金が塗られているからである」
とあり、使節が秀吉との謁見後に公家の案内で広間や台所など聚楽第の主要部分を見学しています。しかし、大坂城天守を表す時に用いた「主城および財宝を所蔵してある塔」に該当する言葉はありません。使節の聚楽第見学コースにも天守は含まれていないようです。
聚楽第は関白の公邸という性格がありますが、大坂城は豊臣秀吉の個人の城です。大坂城天守は豊臣秀吉のコレクションを展示する「豊臣秀吉博物館」として使われています。大坂城天守は城主の彼が案内人を務める大坂城見学コースに含まれています。自らの案内で天守を訪問者のみならず、その御供の者まで積極的に見せている様子がわかります。
城主である秀吉自ら天守を含む城内の隅々まで、訪問者の御供の者まで半ば強制的に案内することは相手への歓迎の意を示すと同時に城主の財力ならびに権力を見せつけるという政治的な意図があります。つまり、大坂城の天守には秀吉の力を訪問者に見せつけるという役割があります。
また、見学コースに天守が含まれる場合は必ず秀吉自ら案内しています。秀吉がいる状態で天守への案内役を他の者に任させると天守に登っている訪問者と案内役が秀吉がいる御殿を見下すという位置関係になります。秀吉は訪問者に見下されることを嫌ったのでしょう。
前述の『輝元公上洛日記』の8月7日の項にあるように、毛利は秀吉の囲碁を観戦した後に秀吉の命を受けた豊臣秀長らの案内で聚楽第を見学し、その後に秀吉は姫子(秀吉の養女か側室)を抱いて、毛利らの雑談に加わっているため、毛利が秀長らの案内で聚楽第見学をした時に秀吉が聚楽第にいたことがわかります。
秀吉が聚楽第にいるにも関わらず聚楽第内部の案内を他の者へ任せたのは、聚楽第には天守のような高層建造物が存在せず、毛利らが秀吉のいる御殿を見下せる場所が存在しないからと推測できます。
天正16年の聚楽第行幸の公式記録の『聚楽行幸記』(『聚楽第行幸記』とも)、その4年後の天正20年(1592)は『天正二十年聚楽第行幸記』という公式記録があります。
『聚楽行幸記』は様々な写本がありますが、大阪城天守閣蔵「聚楽行幸記」は秀吉の朱印があることから原本と考えられています。竹内洪介 石塚晴通「大阪城天守閣蔵『聚楽行幸記』解題・翻刻」(『古代中世文学論考第38集』 編 古代中世文学論考刊行会)に解題と翻刻したものが掲載されています。
天正20年の聚楽第行幸を記録したものは存在しないと長年考えられていましたが、竹内洪介氏が柳沢昌紀氏が所蔵されている典籍の中から発見され、「『天正二十年聚楽第行幸記』解題・翻刻」(『古代中世文学論考第40集』 編 古代中世文学論考刊行会)に解題と翻刻したものを掲載されています。
2度の行幸に関する記録には「天皇が天守を登られた」というような記述は見当たらず、天皇は2度の聚楽第行幸で天守へ行っていないことがわかります。
『天正二十年聚楽第行幸記』では「汀には龍頭鷁首をそうへきつかなせ給ふ御船の御あそひなとあるへきを此度は還幸いそかせ給へは儲の御所には残多そききえ給ふ」と聚楽第の池の渚に舟遊びのための船がつないであり、舟遊びができる用意は整っていましたが、天皇が御所へ戻られる還幸の日が迫っていたことから行われなかったということが記載されています。
天正20年の聚楽第行幸で天皇を天守へ案内する計画があり、舟遊びと同様に日程の都合で中止になったのであれば、『天正二十年聚楽第行幸記』に中止になった舟遊びと同様にそのことが記載されたはずです。天正20年の聚楽第行幸では天皇を天守へ案内する計画もなかったようです。
このように誰にも登らせた記録がない聚楽第の天主もしくは殿主と呼ばれる建造物は大坂城天守のように訪問者へ見せるための施設ではないようです。
疑問点3 なぜ天主に居住者がいるのか
前述の『兼見卿記』の天正18年(1590)1月18日の項などで豊臣秀吉の側室の摩阿姫(前田利家の三女。後に加賀殿と呼ばれる)が聚楽天主に住んでいたことから吉田兼見は彼女のことを「聚楽天主」と記載しています。
前述の桜井成広氏は西本願寺飛雲閣が聚楽第の天守を移築したという説を唱えられています。そのため、飛雲閣の構造から聚楽第の天守に人が住んでいることには疑問に感じられないようです。ただ、前述のとおり飛雲閣には文禄5年(1596)の伏見大地震の痕跡がなく、境内の大半が元和3年(1617)の火災で消失していることから、現在では聚楽第からの移築ではないという見解が主流です。
一般的に天守に住んだ人物は安土城天主に住んだ織田信長だけだと云われています。なぜ、聚楽第の天守に人が住んでいたのでしょうか。
安土城天主は城主である信長の政務の場、居住の場、自ら訪問者を案内して見せるという3つの役割があると考えられています。聚楽第の天守には政務の場である表御殿と、前述のように主自ら積極的に訪問者を案内して見せるという役割はありません。
聚楽第の天主の主な役割が居住の場なら、絵画史料の天守のように高層である必要はありません。居住だけが役割ならば平屋か2階建てであれば十分なはずです。余談ですが、階段しか高層階への移動手段がない天守の高層階は居住には適さないです。
聚楽第の天守への3つの疑問点から「聚楽天主=絵画史料に描かれているような5層の天守があった」ということは断定できません。
天守が存在したにもかかわらず、天守があった場所の地名が天守と関係がないものになる可能性は否定できませんが、誰も登らせなかった点と居住者がいる点に関しては納得できる解答が得られません。
聚楽第には絵画史料にあるような5層の天守は存在しなかった可能性が極めて高いです。
◆聚楽第の天主や殿主という建造物は何を意味するのか
前述のように3つの疑問点から絵画史料にあるような5層の天守がなかった可能性が高いです。
では、文献史料にある聚楽第の天主や殿主という建造物は何を意味するのかという問題が生じます。前述の3つの疑問点を論点に、想定されるケースを2つ考えて見ます。
a 2層か3層の天守の場合
天守を現存、復原を問わず見ることができる天守の画像、もしくは大坂城など現存しない天守の推定復原図を見れば、視覚的に天守はこのような建造物ということが何となくわかるような気がします。
しかし、天守を言葉で説明するのは難しいようです。何となく分かっているようで分からない言葉のようで、天守の説明がない書籍もあります。
色々な書籍で調べてみると天守には2層から3層という隅櫓と高さの面では変わらない天守もあれば、5層など高層の天守もあります。必ずしも我々が天守としてイメージするような5層のような高層の建物である必要ではないようです。
天守の概念を自分なりにまとめてみると「城主の権威を示す目的で建造された2層以上の城側に窓がある櫓建築」ということになります。櫓は城外を見張るための施設です。そのため、城内側に窓はありません。天守は城主が登って眺望を楽しむ目的があるため、櫓と異なり城内側にも窓があり、天守から城主が住む御殿を見下ろすことができます。
聚楽第の天主、もしくは殿主は天守の概念に従えば「2層以上の第内側に窓がある櫓建築」ということになります。つまり、2層や3層でも天守です。
前述の多門町から聚楽第に多門櫓の存在が推測できます。多門櫓は門櫓や隅櫓を結ぶ櫓です。聚楽第に多門櫓と櫓があったと推測できます。
当時の人は隅櫓と天守の明確な区別はつかなかったはずです。そのため、2層か3層の天主もしくは殿主という名称の建造物を天守ではなく隅櫓と考えた結果、天守に関する伝承と地名が残らなかったという考え方ができます。
天守があるのなら隅櫓よりも天守の方が階層が多いというように天守と隅櫓の高さを変えていた可能性も考えられます。しかしながら、聚楽第に2層か3層の天守が存在したのなら、隅櫓よりも外観は立派なはずで、隅櫓との外観の区別は容易なはずです。2層や3層でも当時としては高層建造物のため周囲から見えたはずです。ただ、聚楽第天守同様、何らかの理由で伝承や地名が残らなかった可能性も否定できません。
しかし、2層や3層でも天守です。存在するのも関わらず、聚楽第を訪問した天皇や外交使節、諸大名など誰にも登らせなかったことに疑問が残ります。
さらに、聚楽第に天守閣に相当する天守が存在するのなら『駒井日記』の文禄4年(1595)4月10日の聚楽第の曲輪と、各曲輪の周囲の石垣の長さなどを記載している記事に、天守という聚楽第にとって重要であろう建造物に関する記述がないことも疑問に感じます。
結局、2層や3層の天守でも全ての疑問点が解消されません。
b 聚楽第の天守(殿主)という名称の建造物は天守(俗称の天守閣)を意味しない場合
前記のように聚楽第の天主、もしくは殿主は天守(俗称の天守閣)では、疑問点が解消できません。発想を大きく変えることで疑問点に対する納得できる解答を得ました。
○安土城以前の天主の意味
発想の転換のきっかけは平成18年10月15日に滋賀県立安土城考古博物館が主催したシンポジウム『信長の城・秀吉の城』を基に書籍化した同名の書籍(編・出版 滋賀県立安土城考古博物館)の中で、木戸雅寿氏が講演された「天主から天守」の記述を見たことです。
その中で、文献史料にある安土城以前の天主(木戸氏は豊臣秀吉が天守閣と呼ばれている建造物を天主から天守と言い換えたと考えられ、意図的に二つの言葉を使い分けをされています。この項目では同氏の使い分けに従って記載します)の記述の内容を総合され、特徴を4点挙げられています。
要約すると安土城以前の天主には「座敷の間があり、城主がその座敷で居住している」(1点目と3点目)、「1階から2階ぐらいの建物」(2点目)、「城主が討ち死をしているシーンがいくつか見られる」(4点目)です。
木戸氏が天守の概念を安土城以前の天主と以後で区切るのは、安土城の天主や豊臣期の天守のような高層の天守と安土城以前の天主は、同一名称の建造物でも、全く異なる建造物だからです。
また、同氏は主な建物を意味する主殿から転じて、殿主、天主、天守になったことを挙げ、安土城以前の天主を城主の居住空間とされています。さらに、城内の重要な施設である城主の居住空間である殿舎(普通は平屋)と、防御施設としての櫓の二つとし、安土城以前の天主の定義を
「この平屋の御殿を当時の人が「天主」と呼べばそれは「天主」であり、櫓形式の物を「天主」と読んでいたとしたら、それが「天主」になるということです。」(『信長の城・秀吉の城』P75から76より引用)
とあります。前記の4点の特徴と合わせて考えると、安土城以前の天主の定義は「城の櫓か、城主が居住する御殿のうち、当時の人が天主と呼んでいる建造物」ということになります。
聚楽第の天主(殿主)が安土城以前の天主、安土城の天主、豊臣期の天守のうち、どの天主(天守)に該当するかで、櫓、城主の居住空間である御殿、居住空間と政務の場(奥御殿と表御殿を兼ねている)に加えて訪問者に見せる役割がある高層建築の安土城天主、訪問者に見せる役割のみがある大坂城天守のような高層建築と大きく意味合いが異なります。
織田信長が安土城天主を「天主」と命名した理由は安土城天主を既存の城の城主の御殿である天主の延長と考えたのかもしれません。そのことで天主の言葉の意味に現在の天守閣の概念が加わり、天守という言葉だけでは御殿と天守閣のどちらを指すかわかりにくくなったようです。
○聚楽第の天主(殿主)が意味するのは天主か天守か?
前述のように聚楽第の天主に居住していたことがわかります。通常の櫓は居住が目的ではなく、城外への見張りを目的に建てられているため、居住者がいる聚楽第の天主が櫓である可能性は除外されます。聚楽第の天主の「天主」が意味するのは安土城以前の天守である城主の居住空間の御殿である天主か、安土城天主、豊臣期天守のどちらでしょうか。
まず、聚楽第の天主が安土城天主に該当するかを考えてみます。文献史料から聚楽第の天主には安土城天主の役割の1つである居住空間は確認できますが、政務の場ではなく、天皇や外交使節、毛利ら訪問者を案内してないことから、見せる機能はなく、安土城天主に該当するような天主を意味する建造物ではありません。聚楽第の天主は安土城天主の天主には該当しません。
次に聚楽第の天主の「天主」が安土城以前の天主か、豊臣期の天守のどちらを意味するかを考えてみる必要があります。
木戸氏の講演テーマ「天主から天守へ」の主旨は秀吉が天主を天守に言い換えたというものです。同氏は文献史料に記載されている天主や天守などを示す用語を「表1 文献に現れる天主・天守一覧」という表にまとめられ、秀吉は何らかの意図で天正11年(1573)以降の朱印状から天主から天守という言葉に置き換えたとされています。この表には掲載事例が少なく、聚楽天主ならびに聚楽第の殿主は掲載されていません。
置き換えの理由を第二部のパネルディスカッション(参加者 乗岡実氏、加藤理文氏、木戸雅寿氏 コーディネーター 中井均氏)の中では織田信長と豊臣秀吉の天下への姿勢の違いとされていますが、明確な答えは出ていません。私は安土城以前の天主である城主の御殿と、安土城天主ならびに豊臣期の天守という新しい概念である高層櫓建築(現代の我々がイメージする天守閣)を区別すると意図があるという考え方ができると思います。
前記の『駒井日記』の記述の中で聚楽天主を示す言葉として殿主を使っていますが、文禄3年(1594)の3月18日と、同月20日に淀城天守を伏見城へ移築する記事の中で、淀城天守を示す言葉として「淀天守」もしくは「淀之天守」と記載しているように豊臣期の城の天守を示す言葉として天守を使っています。駒井は天主に関する記録を残した山科と吉田と異なり、秀次の家臣という政権側にいる人物です。
彼が政権側の意向で「天主(殿主)を城主の御殿」、「天守を安土城天主ならびに豊臣期の天守のような高層櫓建築」という意味で意図的に使い分けているならば、聚楽天主は安土城以前の天主、つまり城主(聚楽第の主)の居住する御殿を指します。しかしながら、日記は他人が読むことを想定しないため、駒井が天主と殿主を別の言葉として使い分けているのか、単なる当て字かは断定できません。
現時点では、豊臣政権内で御殿を意味する天主と高層櫓建築を意味する天守の意図的な使い分けが行われていたのかは不明です。聚楽天主という名称だけでどちらを意味するのかは断定できません。今後の研究により豊臣政権内で「天主(殿主)=城主が居住する御殿」、「天守=安土城天主ならびに豊臣期天守のような高層櫓建築」という明確な意図により使い分けがなされていると証明されれば、聚楽第の天守は聚楽天主という名称から、城主が居住する御殿ということが推測できます。
○役割から考える聚楽第の天主と殿主の「天主」の意味
現時点では豊臣政権内で天主と天守という二つの言葉を明確な意図を持って使い分けをしているのか不明なため、聚楽天主という名称から安土城以前の天主か豊臣期の天守のどちらは断定できません。
次は文献史料などから推測できる聚楽第の天主(殿主)の「天主」が、どちらを意味するのか考えてみます。
聚楽第の主である秀吉と秀次が天皇、外交使節、諸大名を聚楽第の天守を案内したいう記録がないことから聚楽第の天守を訪問者に積極的に見せている様子がない、つまり、聚楽第の天守は豊臣期の天守のように訪問者を案内して見せるという役割はなかったと考えられます。
前述のように聚楽天主には摩阿姫が居住していたと推測されるため、居住空間の役割があると推測できます。安土城天主とそれ以降の天守に住んでいたのは織田信長のみと云われています。しかし、安土城以前の天主は城主の居住空間である御殿です。人が住む目的で建てられています。
居住空間という役割があり、大坂城天守のように見せる役割がないという点から、聚楽天主は「2層以上の城内側に窓がある櫓建築」という安土城天主や豊臣期の天守には該当せず、安土城以前の天主、つまり、城主の居住空間である御殿(奥御殿)を意味するのではないかと考えられます。
聚楽天主を聚楽第の奥御殿と考えると、疑問点1の聚楽第の天守を由来とする地名、天守を移築した、もしくは天守が存在したという伝承が残らなかった理由を「聚楽第には安土城天主や大坂城天守に該当するような建築物が存在しない」。
疑問点2の聚楽第の天守に登った人がいない理由を「聚楽第の天主(殿主)は奥御殿であり、天守のように見せる目的で建造されていないため登ることができない」。
疑問点3である聚楽第の天守に人が住んでいる理由を「城主の居住空間である奥御殿だから人が住むのは当然」と説明できます。
聚楽第の天守を奥御殿と位置づけることで前記の3つの疑問点が全て解決します。
◆まとめ
聚楽第には聚楽天主、もしくは殿主と呼ばれる建造物はありました。ただ、現時点では第内のどの場所にあったのか、何階建てかなど聚楽天主の概要は不明です。
私が前記の3つの疑問点への解答を探るという方法で導き出した結論は、「聚楽第には聚楽天主、もしくは殿主という名称の奥御殿はあったが、絵画史料に描かれているような天守に該当するような建造物は存在しない」です。
さらに『駒井日記』の文禄4年(1595)4月10日の聚楽第に関する記事に城主の権威を示すという聚楽第にとって重要な建造物であるはずの高層櫓建築である天守を記載しなかった理由も、「存在していないから記載しようがない」、数mから十数mの高さがあると推測される天守台の地形的な痕跡がない理由も「高層櫓建築である天守が存在しないから天守の土台である天守台も存在せず、地形的痕跡は残らない」と考えられます。
しかし、現時点では情報不足の観は否定できません。
「聚楽第本丸跡地をくまなく発掘調査を行い、天守ならびに天守台の痕跡が出るか出ないかで結論が出せる」と考える人もいるかもしれませんが、聚楽第跡地は民家が建ち並び、大規模な発掘調査は不可能です。
しかも、聚楽第は破却後から町地が建ち並ぶまでは、上質の土壁の材料である聚楽土の採取が行われたことにより、聚楽第や聚楽第城下の大名屋敷などの建物の柱跡の遺構はほとんどが壊されています。考古学の分野から聚楽第の天守の有無を立証するのは困難です。
もし、聚楽第跡の表面波探査の再度実施、もしくは発掘調査で本丸の隅櫓があると想定される箇所を全て調査し、「本丸のある隅櫓の周囲の堀の幅が本丸の他の隅櫓より明らかに広い」という結果を得られたのなら、そこに天守があるという推測も成り立ちます。
今後、発掘調査や表面波探査、新発見を含む文献史料の調査が進み、新たな聚楽第の天守に関する記述が見つかれば、文献史料にある聚楽第の天守(殿主)の概要がわかるはずです。その時をとても楽しみにしています。
〇追記
堺市博物館のHPの企画展「豊臣秀吉と堺」のページ(別ウインドウで開きます)には図録「豊臣秀吉と堺」(編集・発行 堺市博物館)の中の3つの論考が参考資料として掲載されています。その中の宇野千代子氏の論考の「聚楽第行幸図屏風の修理―豊臣秀吉と堺―」の中に天守に関する気になる記述があります。
「天守閣は補筆であろう。痛みやすい本紙の端に位置することもあり、同じ位置に描かれていた天守閣の絵が損傷したため描き直された可能性が高いと思われるが、本来描かれていなかった所に描き加えられた可能性も考えておくべきだろう」
とあり、堺市博物館蔵の「聚楽第行幸図屏風」の天守は描き直された可能性が高いとしつつも、元々は何も描かれていなかった箇所に天守が場所に描き加えられた可能性があることを示唆されています。
「聚楽第行幸図屏風」の天守は三井記念美術館蔵「聚楽第図屏風」など他の絵画史料の聚楽第天守に比べて明らかに小さいです。「聚楽第行幸図屏風」は天守が描かれていないとしても構図としての違和感がないため、天守は描き加えられた可能性が高いと個人的に考えます。
「聚楽第行幸図屏風」の成立年代は安土桃山時代から江戸時代初期です。成立当初の「聚楽第行幸図屏風」に天守がないのであれば、「絵師が聚楽第に天守がないと知っていたから天守を描かなかったが、補筆した絵師が聚楽第に関する他の絵画史料に天守が描かれていることから聚楽第に天守があると考えてわざわざ描き加えた」という考え方ができます。そうであるならば、「聚楽第行幸図屏風」は聚楽第に天守がない新たな根拠になります。
ただ、「聚楽第行幸図屏風の修理」によると当初の「聚楽第行幸図屏風」は六曲一双(右隻と左隻がそれぞれ6枚づつ。合計12枚)だったのが、左隻のみの六曲一隻(6枚)に改められ、何らかの理由で第1扇と第4扇が失われ、第2扇と第3扇を右隻、第5扇と第6扇を左隻とする二曲一双(合計4枚)の現在の形になっています。
失われた第4扇に何が描かれていたのはわかりません。第3扇に描かれている聚楽第本丸の上と右、下には堀がありますが、左には堀が描かれていないです。つまり、第4扇にも聚楽第本丸の建物が描かれていると考えられます。そのため、第4扇に天守が描かれ、「聚楽第行幸図屏風」が現在の形に改められた時に現在の天守が描かれている位置に第4扇で描かれていた天守を縮小して描き加えた可能性もあります。
現在の「聚楽第行幸図屏風」の天守が描き加えられたことが判明したとしても、失われた箇所に天守がないということを立証しない限り、「聚楽第行幸図屏風」は聚楽第に天守がなかったことの根拠にはならないです。